「Food Watch Japan」というサイトで、味の素KK特別顧問・歌田勝弘氏のインタビューが掲載されている。記事は続いているが、今回はそのうち第2回までを読んだお話。
・風説・風評との闘いは創業期から/インタビュー:味の素特別顧問歌田勝弘氏(1)
・広報室の設置で社会との新しい関係を築いた/インタビュー:味の素特別顧問歌田勝弘氏(2)
味の素KKの歴史は化学調味料=うま味調味料の歴史だからして、その歴史を知る人物の話はとても興味深い。
| この調味料の商品名については、池田博士は「味精」(みせい)という名前を考えました。しかし、二代目三郎助は、どうもそれじゃ売れないだろうと思った。それで考えて命名したのが「味の素」です。 |
「味の素」って名前は秀逸だったよねえ。
味の素の製法特許が切れた時に大量に出現した他社製品のブランド名を見ても、ね。(「化学調味料関係のとりあえずのメモ(その6)」参照)
味の素に関する風評についても言及されている。
うちのブログでもこの話題について書いたことがある(「化学調味料関係のとりあえずのメモ(その3)」)のだけど、そこには書いていない話が出ていて面白かった。
| そもそもなぜそんな説が出て来たのか、そこはわからないのです。一説によると、当時の「味の素」の原料は小麦のタンパク質だったのですが、小麦粉を溶かしたものを樽に入れて大八車で運んで来て、それを工場の前でひっくり返してしまって、そのどろどろしたものがこぼれてニョロニョロニョロっと広がったのがヘビに見えたのではないかとかと言いますが、よくわからない。 最初は巷の噂でした。昔の盛り場や縁日には、ヘビを見せてお客を集めて薬を売る人が現れたものですが、その人たちが「今売れ出している『味の素』というのは実はこれだ」みたいなことを言い出したようです。 ところが、そのデマが雑誌に掲載されるようになります。たとえば、宮武外骨(1867―1955/著述家、編集者)が出していた「スコブル」という雑誌の大正7(1918)年10月1日号に「面白い懸賞」という記事があって、これはヘビのイラストを示しておいて「『味の素』の原料は何か」と書いたものでした。また、同じく雑誌「赤」の大正8(1919)年10月1日号には、「文明的新調味料味の素」と書いた吸い物椀から数匹のヘビがはい出ているイラストが掲載されました。 |
宮武外骨については、
| 宮武外骨が著書『一癖随筆』(1922[大正11]年4月)の中で、 「味の素の原料は,豆や麦ばかりでなく,青大将をも使っている…….味の素本舗では全国からヘビを集めています」 と書いたのだそうだ。このせいで鈴木商店にはヘビの買い取り価格の問い合わせが来たりしたという。 |
という話は知っていたけど(「化学調味料関係のとりあえずのメモ(その3)」)、自分の随筆だけでなく雑誌にまで書いてたんだから、宮武外骨は本当にそう思っていたのか味の素に何か恨みでもあったのか……。
このインタビュー記事には、これらの風評に対して社長名で出された声明文広告「誓て天下に聲明す 味の素は斷じて蛇を原料とせず」の全文が掲載されている。
「原料ヘビ説」はいずれ終息したそうだが、マクドナルドの食用ミミズ説もそうだけど、こういうウワサは新しいものが日常に入っていく途中の段階で出てくるものなんだろうね。完全に日常の「そこらにある当たり前のもの」となってしまえばそんなことないんだろうけど、まだ日常に組みこまれていない「他者」の段階での不安がそういう形になるという気がする。
あと興味深かったのは、「「ブレイン・メディシン説」を完全無視」という話。
この話も当ブログでは「化学調味料関係のとりあえずのメモ(その3)」で書いたけれども、「グルタミン酸を摂ると頭がよくなる」という説。
| あの頃、私は営業の第一線にいたのですが、「リーダーズ・ダイジェスト」の記事を読んだときの正直な気持ちを言えば、「これはうまい話が来たな」と思ったんです。ところが、トップからは絶対にその話を営業に使ってはいかんという命令が出たのです。ですから、会社としてはこれを宣伝には一切使いませんでした。
ブレイン・メディシン説は、グルタミン酸ソーダはアミノ酸の一種だから、これに頭の働きをよくする効果があるだろうといった話です。それをある科学者が言い出したことには違いありませんが、実験を重ねるなど深い追究はしていない話ですから、この説をうっかり宣伝に使うのはまずいという判断だったのでしょう。 |
この自制は、今となっては「当たり前」と捉えられるかもしれないが、当時の営業のことを思うと卓見と言わざるを得ない。
ちなみに今でも、味の素KKのサイトのQ&Aにはこんな記述がある。
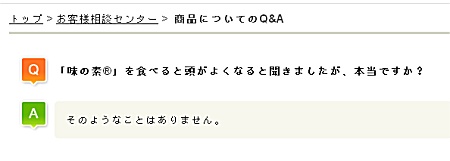
そこからは昭和40年代の「マウスにグルタミン酸ソーダを投与した結果、脳の視床下部に損傷があった」という話と「チャイニーズ・レストラン・シンドローム」の話となり第1回は終わる(この話は当ブログでは「化学調味料関係のとりあえずのメモ(その1)」や「化学調味料関係のとりあえずのメモ(その5)」など)。味の素の歴史は、会社(製品)と社会との情報コミュニケーションの歴史だとも言えるのだろう。
※だからこそ上記の「自制」が効いてくる。情報コミュニケーションの中で、情報の正確さよりも自らの利益を優先すると受け取られることは致命的だから。
「化学調味料関係のとりあえずのメモ(その3)」には、『脳ブームの迷信』(藤田一郎著)について、
| 「私の知る限り、「『味の素』を食べると頭が良くなる」という宣伝を発売元が行ったことはなく、この迷信の発信源は林髞だろう」と結論づけている。 |
と書いたが、このインタビューによれば林髞のさらに前にアメリカの雑誌『リーダーズ・ダイジェスト』の記事があったということになる。知らない事実が広がってくるねえ。
第2回のインタビュー記事では、いち早く広報室を設置したという話になる。
「パブリックリレーション(public relations)」をいち早く導入したのは、第1回で語られたような「情報」的商品の特性上、必然だったのかもしれない。
ここでは「化学調味料」という名称から「うま味調味料」という名前への変遷と、「うまみ umami」という国際語の定着と普及について語られる。
ただ、インタビュー記事として第1回に比べて迫力が落ちると感じた。
おそらくそれは「化学調味料」という名称から「うま味調味料」という名前への変遷の話の中で、「合成法」という製造法への言及がないことが大きいのだろうと思う。
「化学調味料関係のとりあえずのメモ(その5)」に書いたが、「味の素は石油からできている! うっきー!」という感情的な批判は、実態に対してはかなり歪んでいる。
「グルタミン酸ナトリウムは、かつては石油から合成法で製造されていた」という言及に対して、より正確を期して言うならば、
| 確かにそうだが、その「かつて」とは、1909年からの100年のうち1962~1972年の11年間であり、その生産量は味の素KKという一企業がその期間中に製造したMSGの18%に過ぎない(業界全体の生産量のだいたい15%くらい)。 |
という答えになる。
……とはいえ、「化学調味料」という名称やそのイメージに対して合成法という製造法は圧倒的な影響力を持ったはずで、これについて触れないことは、話の迫力や説得力はかなり減じられると言わざるを得ない。
※このことをはてブ(twitterと連動させてる)に書いたら、このインタビュー記事をまとめた方からtwitterでこんなお返事をもらった。
こちらも興味深い。ただ、化学調味料の名称の話の中で合成法の話を一切出さないのはそれはそれでモヤモヤする。確かにイメージと比べて格段に生産量が少なかったけど、イメージに決定的な影響は与えたわけだから。 / “広報室の設置で社会との新…” http://t.co/82hWfuwtQY
— ひえたろう@笑顔と上機嫌こそが最高の化粧 (@hietaro) 2013, 12月 18
@hietaro ごもっともです。実は、”発酵法を採用するまでにはいろいろあったんだ”というお話で、この部分は独立した一つのテーマとして、複数取材を経てルポの形で書くほうがいいと考えました。
— 齋藤訓之 (@Kosetsusha) 2013, 12月 19
そういうことならばこのルポに大いに期待したい。
とても面白く意義深いものになると思う。
編集部はネット上の反応には気を砕いているようで、「誓て天下に聲明す 味の素は斷じて蛇を原料とせず」の全文を掲載したのも、記事を見て「ほしい」とつぶやいた人に反応したものだった。
12月19日現在、第3回のインタビューも掲載されており、そこからさらに「つづく」となっている。
・新しい流通と新しい消費を正しく受け止めた/インタビュー:味の素特別顧問歌田勝弘氏(3)
今後のインタビューも楽しみにしたい。
これら過去の化学調味料関連のエントリを書くにあたっていろんな会社にメールで問い合わせたが、中でも味の素KKはかなり丁寧な対応をしてくれた。
他の記事を読んでも、「Food Watch Japan」というサイトは非常にいいサイトのようだ。
さっと見ただけでもこのあたりはとても面白かった。
・しょうゆ容器の開発競争
・「美味しんぼ/醤油の神秘」の誤り
これはまったく関係ない話なのだけど、『リーダーズ・ダイジェスト』という雑誌が出てきたので。
この雑誌はラーメン好きには少しだけ関係がある。
味噌ラーメン開発のきっかけとなったのは『リーダーズ・ダイジェスト』の記事だった。
この中でマギー社の社長は「日本人は味噌という素晴らしいソースをもちながら、それを活用していない」語っていた。
この言葉を念頭に、札幌の「味の三平」店主の大宮守人氏が味噌ラーメンを開発したというお話。
これはかなり有名な話で、ラーメンの起源の話になると必ず出てくる。
突然食いたくなったものリスト:
本日のBGM:
Beginner /三谷幸喜 AKB48 SKE48 NMB48

最近のコメント