どこに書くべきか悩んだんだけども……。
mixiにはCDのレビューのページがあって、好きなアルバムにレビューをつけることができる。
その中にはFLOWER TRAVELLIN’BANDのアルバムもあって、たまたま読んだら、どうしてもツッコミを入れたいレビューを見つけてしまった。
レビューっていうのはきっとそのレビュー自体への「反論」は想定されてないだろうし、実際、そういう場所も用意されていない。レビューの下にコメント欄でもあれば別なんだろうけど。
かといってわざわざこの人の日記に出向いていって書くのもナンだし、だいたい3年以上前のレビューだし……、でもやっぱりツッコミは入れておきたい……。ということで、ここに書くことにした。
レビューはFLOWER TRAVELLIN’BANDの『MADE IN JAPAN』というアルバムについてのもの。
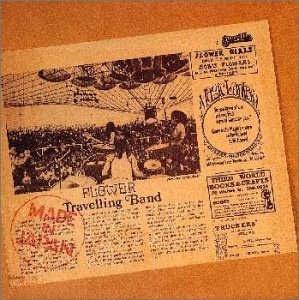
FLOWER TRAVELLIN’BAND『Made In Japan』
| 日本人で初めてアメリカで成功をつかんだバンド「フラワー・トラベリン・バンド」のセカンドアルバム。
正直筆者の嫌いなタイプのバンドである。理由を説明しよう。 日本人が自ら欧米生まれのロックンロールを演奏するとき、必ず2つのアプローチのどちらかを選ばなければいけない。それは歌詞を英語で歌うか、日本語で歌うかである。同世代の「はっぴぃえんど」が「バッファロー・スプリング・フィールド」を意識した西洋風の演奏に「です・ます」調の粋な歌詞を乗せたロックを展開したのに対し、この「フラワー・トラベリン・バンド」は逆に東洋風の音階の演奏で日本人らしさを出し、それらに英語の詩を乗せたロックを展開した。 しかしその年のアウォードを「はっぴぃえんど」が受賞したことや、米国紙TIMEに特集されたのも「はっぴぃえんど」なことからも明らかなように、「はっぴぃえんど」的なアプローチが結果的に日本人としてのアイデンティティを保持したロックの展開であったのだ。 受賞等を無視したとしても、東洋的音階にこだわるあまり全ての曲が似たような印象しか持てないし、ジョー(山中)の甲高い奇声に近いボーカルは耳障りだ。英詩にこだわったのはプロデューサーでもあった内田裕也だが、歌詞はあくまで楽器で伝えられない詩的表現を担っているだけなのであって、楽器でイカした演奏をすれば歌詞なぞ何語だろうと構わないのだ。その好例がタイトな演奏にしてテクニシャン揃いの集団「はっぴぃえんど」であり、そのハードな演奏に相反する「です・ます」調の丁寧語で綴られる歌詞のコントラストが面白いのであって、演奏に重点を置くことはミュージシャンの基本であろう。 その意味では、英詩と東洋音階にのみ執着するこのグループのアルバムは正直買ったことを後悔するほど価値の無い1枚であった。ファンの人ごめんなさい。 |
(原文は改行がない。読みやすいように引用者[hietaro]が改行を足した)
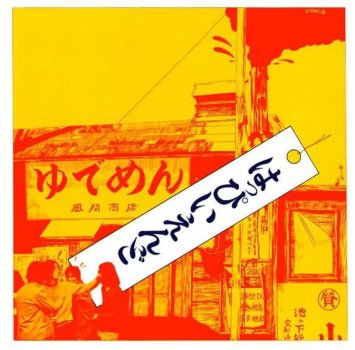
はっぴいえんど『はっぴいえんど』
この「レビュー」について、恐縮ながらツッコミを入れさせていただく。
| 日本人で初めてアメリカで成功をつかんだバンド「フラワー・トラベリン・バンド」のセカンドアルバム。 |
FLOWERが一番「成功」したのはカナダだと思うけども、アメリカでも「成功」したのかな?
カナダでの「成功」でさえ、「成功」と言えるほどのものではなかったと思うよ。
それに『MADE IN JAPAN』はセカンドじゃなくてサードだ。
|
正直筆者の嫌いなタイプのバンドである。理由を説明しよう。
日本人が自ら欧米生まれのロックンロールを演奏するとき、必ず2つのアプローチのどちらかを選ばなければいけない。それは歌詞を英語で歌うか、日本語で歌うかである。同世代の「はっぴぃえんど」が「バッファロー・スプリング・フィールド」を意識した西洋風の演奏に「です・ます」調の粋な歌詞を乗せたロックを展開したのに対し、この「フラワー・トラベリン・バンド」は逆に東洋風の音階の演奏で日本人らしさを出し、それらに英語の詩を乗せたロックを展開した。 |
まずここで違う。
「日本人が自ら欧米生まれのロックンロールを演奏するとき」に日本人が選んだのは、最終的には「歌詞を英語で歌うか、日本語で歌うか」の「2つのアプローチのどちらか」ではなかった。
実際、FLOWER、はっぴいえんど以降の日本のロック界で「勝利」したのははっぴいえんどの「日本語派」ではない。もちろんFLOWERの「英語派」でもない。勝利したのはそのどちらでもない、「英語混じり日本語」派だったのですよ。
まあそれでも「日本語派が勝利した」という見解もあることは事実で、もしその見解を採ったとしても、このレビュアーは単に「日本語」であること以上に「「です・ます」調の歌詩」であることにまで言及しているのだから、だったらそれ以降の日本のロックの日本語詩の中で、「です・ます」調がどの程度普及したのか、ちゃんと意識してみればいい。恐らく全曲英詩にしたバンドよりも少なかったはずだ。
#この部分、この記述がはっぴいえんどという1バンドの個性について述べているだけなら問題ないのだけれど、この文章の前後(日本人が自ら欧米生まれのロックンロールを演奏するとき……/「はっぴぃえんど」的なアプローチが結果的に……)で一般化した話をしているので話がややこしくなっている。きっとレビュアーの頭の中で整理できないのだと思う。
| しかしその年のアウォードを「はっぴぃえんど」が受賞したことや、米国紙TIMEに特集されたのも「はっぴぃえんど」なことからも明らかなように、「はっぴぃえんど」的なアプローチが結果的に日本人としてのアイデンティティを保持したロックの展開であったのだ。 |
これが「日本人としてのアイデンティティを保持したロックの展開」の根拠になるの? ここから「明らか」なの? あまりつながりは感じられないんだけども。
(「その年のアウォード」ってのは、何年の何の賞のことを言っているんだろう?)
ドメスティックな展開とインターナショナルな展開のどちらを目指したかも大きな違いだと思うけれど、そのあたりの違いは目に入らない?
#ちなみにはっぴいえんどの細野晴臣がその後作ったYMOは結成当初から国際展開を想定していたが、曲はインスト及び英詩だった。そして彼らが用いた東洋的「アイデンティティ」は、欧米で俗化された東洋イメージを逆手に取った、「どこにもない架空のオリエンタリズム」だった。そしてそれが表現されたのは音階や歌詩以上に、ファッションなどヴィジュアルイメージにおいてだった[例えば人民服を着てコカ・コーラを飲みながら麻雀に興じている『SOLID STATE SURVIVOR』のジャケットなど]。彼らが歌詩を日本語にしたのはドメスティック市場へシフトしてから。
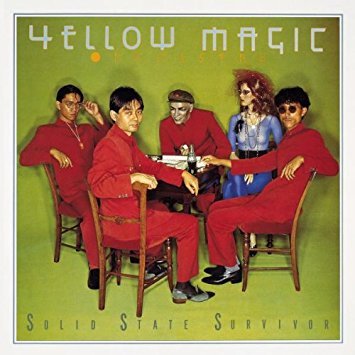
YELLOW MAGIC ORCHESTRA『Solid State Survivor』
もし当時、はっぴいえんどがアメリカやカナダに渡ったとして、それでも彼らは日本語を選んだだろうか?
そしてはっぴいえんどが「米国紙TIMEに特集」された(私は知らなかった)ことを「日本人としてのアイデンティティを保持したロックの展開」の根拠として持ち出すのなら、自身の、FLOWERが「日本人で初めてアメリカで成功をつかんだ」とする見解とはどう整合するんだろう?
「日本人で初めてアメリカで成功を」つかめたのだとしたら、それはそれで「結果的に日本人としてのアイデンティティを保持したロックの展開であった」と言えそうな気がするのだけれど。
| 受賞等を無視したとしても、東洋的音階にこだわるあまり全ての曲が似たような印象しか持てないし、 |
そうは思わないけど、これはまあ個人の見解だから文句を言う筋合いはないね。
しかし東洋的音階だから「全ての曲が似たような印象」になるってのは、まるで「俳句はみんな五七調だから似たような印象しか持てない」とか「雅楽はみんな同じ曲に聞こえるね」と言ってるのと同じような印象しか、私は持てない。
だいたい、『MADE IN JAPAN』ってそんなに東洋的音階を使ってただろうか?
……とここまで書いて、「!」と。
ひょっとしてこの人、『MADE IN JAPAN』じゃなくて『SATORI』について書いてるんじゃないの? なんかそういう気がしてきたな。『SATORI』はセカンドアルバムだし。
なんだそりゃ。
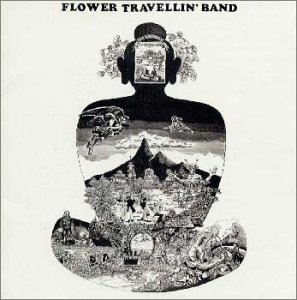
FLOWER TRAVELLIN’BAND『Satori』
| ジョー(山中)の甲高い奇声に近いボーカルは耳障りだ。 |
これは「それは歌詞を英語で歌うか、日本語で歌うかである。」とは全く違う次元の話だよね。いや、好みの問題は重要だし尊重するけども、この文脈で持ってくるのはおかしいでしょ。
| 英詩にこだわったのはプロデューサーでもあった内田裕也だが、歌詞はあくまで楽器で伝えられない詩的表現を担っているだけなのであって、楽器でイカした演奏をすれば歌詞なぞ何語だろうと構わないのだ。 |
それは(今から振り返れば)そうですな。確かにそうだと思う。
しかしそれはきっと、彼らの屍を越えて成り立っている今の「日本のロック」の肩の上から来し方を眺めるからそう見えるんだよ。自分が立っている足場の高さを意識できないのはどうにもなあ。
当時の彼らが捉えていたロックと、自分が考えている(彼らの試行錯誤の末に築かれた)ロックとではその中身が全然違うのかもしれない、とか想像できないかな?
| その好例がタイトな演奏にしてテクニシャン揃いの集団「はっぴぃえんど」であり、そのハードな演奏に相反する「です・ます」調の丁寧語で綴られる歌詞のコントラストが面白いのであって、演奏に重点を置くことはミュージシャンの基本であろう。 |
ん? FLOWERは演奏に重点を置いてないっていうわけ? どうして? これだけ上手いバンドを捕まえて。
| その意味では、英詩と東洋音階にのみ執着するこのグループのアルバムは正直買ったことを後悔するほど価値の無い1枚であった。 |
ああなるほど、「英詩と東洋音階にのみ執着」してるから演奏に重点を置いてないってことになるのか。
論理のつながりが全然わからない。
レビュアーの言う
| 歌詞はあくまで楽器で伝えられない詩的表現を担っているだけなのであって、楽器でイカした演奏をすれば歌詞なぞ何語だろうと構わないのだ |
という意見に純粋に耳を傾けるならば、だったら別に英語だっていいじゃないのかという話にもなるだろう。この論理で行くと、FLOWERが英詩に「執着」したことを非難するのと同じ理由で、はっぴいえんどに対しても「日本語詩(しかもです・ます調)に執着している」と非難するべきなんじゃないのかな。
「楽器でイカした演奏をすれば歌詞なぞ何語だろうと構わない」というのなら、曲の個性ごとに一番合った言語(英語や日本語やその他)を選択するのがベストであって、特定の言語にこだわることは、「イカした演奏」の足を引っ張ることになりかねないということになるはずだ。となれば、この論理は日本語詩の方にアドバンテージを与える理由にはならないはずだ。
しかもはっぴいえんどの曲作りは「詩先」(先に詩を作ってから曲を作る)だったわけで、その意味では詩に縛られているのはむしろはっぴいえんどの方だったという見方だってできる。
#もちろん私はそうは思わないよ。私はFLOWERのアプローチもはっぴいえんどのアプローチもどっちも好きだし納得してる。これはあくまでも「この人の論理で行くなら」というお話。
東洋音階についてはあくまでも好みの問題でしかないように思える。東洋音階を使うから「全ての曲が似たような印象しか持てない」などという言い草は、上にも少し書いたけども東洋の音楽の歴史を真っ向から否定する大胆な意見で(^^;;、とうてい受け入れられない。
結局、この後半の論理は
このバンドは「英詩と東洋音階にのみ執着」しているがゆえに「演奏に重点を置く」という「ミュージシャンの基本」すら外している。だからこのアルバムは「価値の無い1枚」なのだ。
といったあたりに要約できるけども、さすがにこれはねえ。
何というか、最初の1文からかなり事実誤認や事実に対する認識不足が散見されて、いや別にそのこと自体はかまわないのだけれど、しかしそれをもって「理由を説明」しちゃってるのは、どうにも恥ずかしい。
好みの問題として言う分にはまったく問題ないと思うんだよね。「価値の無い1枚」という評価は。これはまったく問題ない。
でも、「正直筆者の嫌いなタイプのバンドである。理由を説明しよう」と書き出したその「理由」が的外れだった場合、じゃあ好きになるのか?といえばそんなことないでしょ。
だったら単に「俺は嫌いだから」でいいんじゃない? 変に一般化した理由付けをしようとするから変な話になる。
……いや、「嫌い」に理由付けする行為はそれほど悪いことじゃないんだと思うよ。ただ、もし理由付けするならもうちょっと説得力を持たせて下さい、という話。
#あと、はっぴいえんどを引き合いに出して嫌いな理由を説明しているのもあまり筋のいい話ではないように思うなあ。はっぴいえんどのアプローチよりもどうだからいい/悪いという話になるのなら、もしはっぴいえんどがなければ評価は変わったのかという疑問も湧いちゃうんだよね。
突然食いたくなったものリスト:
- おにぎりせんべい
本日のBGM:
ロールオーバーゆらのすけ /JACKS

最近のコメント